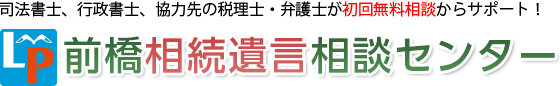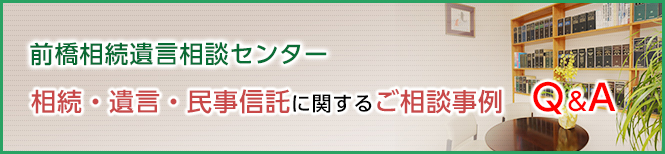2024年04月03日
相続財産調査を進めていますが父の通帳が見つかりません。司法書士の先生、どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(前橋)
こんにちは、前橋在住の40代女性です。先日、同じく前橋に住む父が亡くなりました。
葬儀はすでに近親者のみで前橋の葬儀場で済ませ、現在は父の相続手続きを進めているところです。相続人は母と私の2人ですが、母は父の急な死に憔悴しており、とても相続手続きを一緒に進めていける状況ではありません。私自身、前橋にある飲食店で週5日働いているため時間があまり取れませんが、休みの日に実家に出向き相続財産調査を進めています。
ですが、どれだけ探しても父の退職金が入金されているはずの通帳とキャッシュカードを見つけることができません。今になって父の生前に聞いておけばよかったと後悔していますが、母も銀行口座については聞いていないと言うため途方にくれています。司法書士の先生、これから相続手続きを進めていくためにアドバイスをいただけませんか。(前橋)
A:遺言書や終活ノートなども見つからず財産調査が進まない場合、戸籍謄本を用意して金融機関から残高証明書を取り寄せることが可能です。
財産調査を進めているものの通帳やキャッシュカードが見つからないとのことですが、遺言書や終活ノートが遺されていないかも併せて確認をしてみてください。
故人の使用していた金融口座などの情報を、遺族がすべて把握していることはあまり一般的ではありません。そのため、故人が生前メモなどにまとめている可能性も十分にあります。そのようなものを見つけることができれば、銀行に対して口座の有無や残高証明などの情報開示を請求することが可能です。見つからない場合は、金融機関からの郵便物や銀行の名入れの粗品(ポケットティッシュやメモ帳など)があれば、それを手がかりに問い合わせをしてみましょう。
しかし、どれだけ探しても上記に挙げたものが見つからない場合は、故人の前橋のご自宅や職場の近辺にある銀行に直接問い合わせを行いましょう。ここでの注意点としては、口座の有無や残高証明などの情報開示を請求する場合、請求者が相続人であることを証明するために、戸籍謄本の提出が求められるということです。問い合わせ前に用意をしておきましょう。
今回の前橋のご相談者様のように、相続手続きは面倒事や負担になることも多く、時には思うように手続きが進まず時間がかかってしまうこともあります。また、お仕事の合間に相続手続きを行う場合には、日中にまとまった時間を取ることができずにお悩みになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
前橋在住の相続手続きにお悩みの方やご相談がある方にむけて、前橋相続遺言相談センターでは初回無料相談を実施しております。ご依頼されるかどうかに関わらず、まずはお気軽にお問い合わせいただき、 前橋相続遺言相談センターにご相談者様のお悩みをぜひお聞かせください。相続・遺言に関する専門家の立場から、最適なアドバイスをさせていただきます。
2024年01月09日
Q:司法書士の先生、遺産の中に相続登記が完了していない不動産がありましたが、放置しても大丈夫ですか。(前橋)
私の父は2年前に亡くなっており、私と妹、弟の3人が相続人であったため遺産分割協議を行い、問題なく終わりました。その後しばらくして他に父名義の不動産があることがわかったため、その土地についての遺産分割協議を行おうとしましたが、当時バタバタしていたこともあり頓挫したまま時が経ってしまいました。ところが、先日「相続登記」が義務化されることを知り、その土地はどうしたらよいか困っています。父が亡くなったのは2年前ですので対象外ならよいのですが、とにかく、2024年から施行される相続登記の義務化について教えてください。(前橋)
A:2024年4月1日に相続登記の申請義務化が施行予定です。施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。
今までは、不動産を相続した際に行う不動産の名義変更手続き(相続登記)には、期限の定めがなかったため、名義変更がされないまま、所有者が誰かわからない不動産が多く存在していました。
このような所有者不明の不動産は都市計画の妨げになるだけでなく、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかる事案も増えてきたことにより、今回の法改正(2024年4月1日施行される予定)で相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請義務化により「相続により所有権を取得した(相続が開始した時点)と知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わないと10万円以下の過料の対象となることが決定しています。
これは、施行日前に発生した相続についても対象となるため注意が必要です。ただし、「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられます。とはいえ、相続登記が終わっていない方は早目に手続きを終えておくと安心です。
なお、何らかの事由により、相続登記が進められないという場合には法務局にて「相続人申告登記」を行うことをお勧めします。「相続人申告登記」を申請しておけば期限内に相続登記ができなくても所有者不明とはならず、過料の対象外となります。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2023年10月03日
Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのか司法書士の方に伺います。(前橋)
前橋市在住の会社員です。先日70代の父が前橋市内の病院で亡くなりました。闘病生活が長かったこともあり、私達家族はある程度覚悟できていたと思います。葬儀についても前橋市内の斎場で滞りなく行われました。亡くなってからは、遺品整理を行って遺言書を探したりもしましたが特に見つかりませんでした。相続人は母と私と弟の3人なので、葬儀後や遺品整理の際に遺産分割について話し合いをしました。父の遺産は、父が住んでいた自宅と預貯金が数百万円だけのようです。借金も見つかりませんでしたので、比較的スムーズな相続手続きになるんじゃないかと思います。相続人は家族だけなので、今後揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。そもそも遺産分割協議書は作成しなければならないものなのでしょうか。(前橋)
A:相続手続きに限らず、その後の手続きのためにも遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。
まず、遺産分割協議書は、相続人全員によって遺産分割について話し合われた内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる遺産分配で登記をする場合は遺産分割協議書が必要となります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い相続手続きを進めるので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというわけではありません。しかしながら、相続では思ってもみなかった財産が突然手に入る、非常に揉め事の起こりやすい機会です。仲の良いご家族でも、仲が良いゆえに本音でぶつかり合うことも少なくありません。遺産分割協議書があれば、相続人同士の争い事が起こった際に内容を確認する際に役立ちます。
遺言書のない相続手続きでは、今後の手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
【遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合(全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避
前橋の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。前橋の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、前橋相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。
前橋相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、前橋エリアの皆様をはじめ、前橋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
前橋相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、前橋の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは前橋相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。前橋相続遺言相談センターのスタッフ一同、前橋の皆様、ならびに前橋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談

前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。